こんにちは。
家を建てるには建築確認申請をはじめとするさまざまな許可が必要です。
例えば、都市計画法に基づく開発許可や、農地を宅地に変更する場合の農地転用許可など、土地の用途や規制によって異なります。さらに、建築基準法の接道義務を満たしているかも重要なポイントです。これらの申請を適切に行うことで、安全で快適な住まいづくりが実現します。
今回は備忘録を兼ねて岩手県全域、特に盛岡市と滝沢市に関わるところを簡単にご紹介します。

【建築確認申請前にクリアすべき主な法令・手続き一覧(一般的なケース)】
| 項目 | 内容 | 関連法令 |
| 農地転用 | 農地を宅地などに変更するには、農地法に基づく
「農地転用許可」または「届出」が必要 |
農地法 |
| 開発許可 | 一定規模以上の土地開発には開発許可が必要
(都市計画区域内) |
都市計画法 |
| 都市計画制限の確認 | 建築物の用途や規模に制限あり
用途地域、地区計画、景観条例などを確認 |
都市計画法、
建築基準法、景観法 |
| 道路との接道確認 | 建築物は原則として「幅員4m以上の道路」に2m以上
接していないと建築不可 |
建築基準法第42条 |
| 造成許可・宅地造成等規制法の適用確認 | 傾斜地などで造成を行う場合、許可または届出が必要 | 宅地造成等規制法 |
| 文化財保護区域の確認 | 埋蔵文化財包蔵地内では事前に届出・調査が必要 | 文化財保護法 |
これらは一般的に事前確認しておくべきことの一部になります。本当はこれ以外にもたくさん確認事項はあり、例えば土地の状況や道路状況、近隣地の状態によって確認するべき事柄や必要な申請は増えていきます。また、建てる地域によって条件が異なっていきます。
そんなの見ればわかるじゃんと思うものもありますが、そうもいかないものも多々あります。順不同ですが少し簡単にまとめたものを書いていきます。

1.農地転用
農地を住宅地や商業地、工場用地などの非農業用途に変更することを指します。現状更地であっても登記簿上の地目が田・畑であれば農地転用の許可が必要です。
まずは登記簿上の地目の確認をし、各市町村の窓口で調べるところから始まります。
ここで注意するのは農業振興地域の場合です。こちらに該当する場合、農地転用の前に農振の解除が必要です。
申請する地域によっては数ヶ月に1度の受付もあれば数年に1度の受付になる場合もあります。これは申請する市町村によって変わるので要注意です。
農地転用のポイント
【転用の対象】
- 農地を宅地、駐車場、資材置き場などに変更する場合
- 形状を変えずに使用目的を変更する場合も転用に該当
【許可が必要なケース】
- 市街化区域内の農地は、農業委員会への届出で転用可能
- 市街化調整区域や農業振興地域では、都道府県知事の許可が必要
【許可の基準】
- 立地基準:農地の種類(第1種農地、第2種農地、第3種農地)によって転用の可否が決まる
- 一般基準:事業計画の適正性、周辺農地への影響などが審査される
【手続きの流れ 】
- 農業委員会へ相談 → 申請書類の提出 → 審査・許可 → 地目変更の登記。
細かい訂正などは受付してから随時きますが、問題がなければこのように進みます。
受付時期、審査期間は市町村によって変わりますので、受付~許可証が下りるまでは数ヶ月は余裕を見ていただきたいです。

2.都市計画制限の確認
建築や土地利用を行う際に、その場所にどんな都市計画が定められているかを調べることです。簡単に言うと、「この土地にどんなルールがあるか」を把握する作業です。
色々あるのですが、簡単にいくつかまとめてみます。
用途地域について
土地の使い方(用途)を定めることで、住みやすく安全な街づくりをするための制度です。該当する場所によって建てられる建物の種類や規模が制限されます。
【用途地域の例】
| 分類 | 地域名(例) | 特徴 |
| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 一戸建て中心、静かな住宅街 |
| 商業系 | 商業地域 | 店舗・オフィス・マンションなどが混在 |
| 工業系 | 工業専用地域 | 工場のみ建築可能、住宅は不可 |
建蔽率や容積率もこれらに合わせて違いがあります。第一種低層地域では主に戸建てが中心のエリアになり、建蔽率容積率は他の住居系(第一種住居など…)と比べると小さめになります。外壁後退など隣地との距離を空ける必要があったりしますが、その分周りが住宅街なので隣に商業施設がいきなりできることはありません。
(住宅地では工場やパチンコ店などは建てられない…など)
建蔽率容積率についても建てられる大きさが変わってくるのでそこも含めて検討が必要です。

景観条例について
景観法に基づき、美しい街並みや自然環境を守るためのルールを定めた条例です。
岩手県では「岩手の景観の保全と創造に関する条例」に基づき、景観形成を推進しており、主に建物の色・高さ・形などが制限され、条件に当てはまる建物の設計が求められます。
ちなみに滝沢市・盛岡市は景観行政団体として独自の景観計画を策定しています。
盛岡市の場合
盛岡市の景観条例は、「美しい盛岡」を次世代に継承するために、景観法に基づいて定められたルールです。建築物や工作物の形態・色彩・高さなどに制限を設け、地域の景観を守ることを目的としています。
盛岡市では、景観法に基づき「景観形成地域」と「景観形成重点地域」を設定し、それぞれの地域特性に応じた景観保全・形成を進めています。以下にその概要をまとめました。
景観形成地域とは?
市域全体を対象に、地域の特性に応じて景観形成を誘導するための基本的な区分です。以下の3つの類型に分かれています。
| 類型 | 特徴 | 主な対象地域 |
| 市街地景観地域 | 建物の密集する都市部。色
彩・高さ・形状に配慮 |
盛岡駅周辺、中央通、大通など |
| 田園・丘陵景観地域 | 自然と調和した農地や丘陵地。 | 都南地域、玉山地域の一部 |
| 山地景観地域 | 山並みや森林を背景とした地域。
眺望や自然環境重視 |
姫神山周辺、岩洞湖周辺など |
【市街地景観地域】
- 低層建築物の主な制限内容…色彩は彩度4以下、屋根形状は周囲と調和すること
- 大規模建築物の主な制限内容…高さ制限あり(周辺環境に応じて)、外壁色は落ち着いた色調に限定
【田園・丘陵景観地域】
- 低層建築物の主な制限内容…自然色(緑・茶系)を基本とし、反射性の高い素材は不可
- 大規模建築物の主な制限内容…高さ制限あり、周囲の地形に馴染むよう配置すること
【山地景観地域】
- 低層建築物の主な制限内容…岩手山や姫神山の眺望を妨げないよう高さ制限あり
- 大規模建築物の主な制限内容…色彩は自然環境と調和するものに限定、夜間照明に配慮

景観形成重点地域とは?
盛岡市の景観の「骨格」となる重要な要素を保全・強化するために指定された地域となり、以下のような分類があります。
【眺望景観保全地域】
- 岩手山や姫神山などの眺望を守るため、建物の高さや色彩に制限
- 例:盛岡城跡公園、開運橋、渋民公園などからの眺望領域
- 色彩は周囲の自然と調和するものに限定
【河川景観保全地域】
- 北上川・雫石川・中津川沿いの建築物は水辺景観との調和が求められる
- 河川沿いの建築物や工作物に制限あり
【歴史景観地域】
- 盛岡城跡や鉈屋町など、歴史的建造物や街並みを保全
- 色彩・形状は伝統的な街並みに調和すること
- 建物の外観変更や新築に際して届出が必要
【街路景観地域】
- 幹線道路沿いや旧街道などの景観を整える
- 看板や照明などにも配慮が求められる

基本的には高さや建物形状、色彩が重視され、街並みに調和した建物であることが求められます。
例えば、歴史景観地域では外部に設置する設備の場所も重視され、室外機などが道路側から見ての目立つところにある場合は、目隠しが必要になったりします。
また、平泉などでは歴史的重要な地域が多いためその地域独自の景観の条件があります。
例えば、軒を750mm以上にする、屋根形状は入母屋・切妻・寄棟が望ましい、屋根材外壁材は低彩度色または無彩色を用いるなどなど。
そういった場所ではお店の色彩も落ち着いた色合いのものが多いですね。
コンビニや薬局などは普段と見慣れない色なので何度か通り過ぎた記憶があります…。
それぞれ地域差があるのでそういった建物をみかけるもの楽しく思えますね。

さて、備忘録として書きながら全然内容は進みませんでした。
これでもほんの一部しか書いていないので他の内容もまとめきれるか不安が残りますが、またの機会に道路についてとか、宅造規制についてとか書きたいと思います。





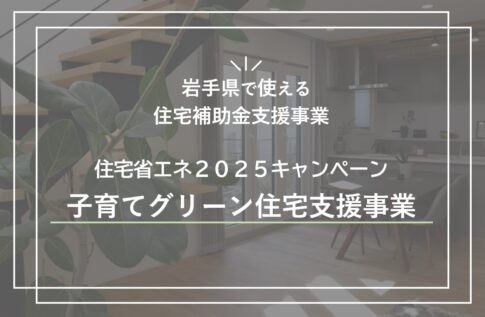



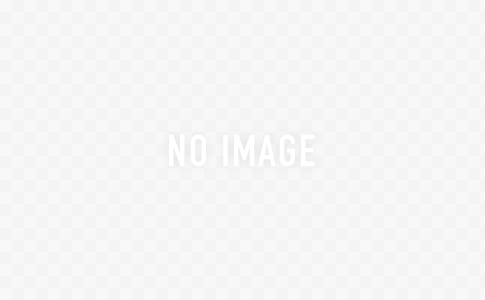


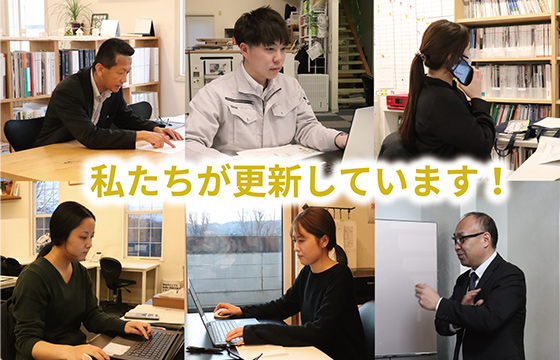

コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。