こんにちはtakedaです。
お家を建てる過程の中でも、「上棟」という日はとても特別な日となります。
しかし、「上棟」と聞いても家づくりが初めての方にはピンとこない言葉かもしれません。
今回は「上棟」とはどんな日か、どのような準備が必要で、当日はどのように作業が進むのかを詳しくご紹介したいと思います。
今回は大共ホームの上棟の流れについてご紹介したいと思います。
- はじめ「上棟」は何か
まず用語についてです。「上棟」とは、一般的には、家の骨組みを組み上げ、屋根の一番上の部材(棟木:むなぎ)を取りつけることを指します。英語では「フレーミング」とも言われる工程で、基礎の上に柱が立ち、梁(はり)や桁(けた)などが組まれて、家の形が一気に姿を現すことです。
大共ホームでの「上棟」の場合は、1日フレーミングと呼び、基本的には1日で1階の壁パネルから最上階の屋根の野地板までを施工することを言います。
家づくりの中でも上棟は特別な1日であり、「家が建つ日」として施主にとっても感慨深い節目となります。工事に関わる職人さんたちのチームワークが一体となって、一日で構造が完成していく様子はまさに圧巻ですね。
- 上棟前日までの準備
・上棟日の決定
上棟日の日程の決め方についてですが、事前に現場監督がお客様と日程を打ち合わせて日付を決めます。
上棟は1日で行う大規模な作業であるため、天候が非常に重要です。雨が降ると滑りやすくなるため、安全性が損なわれますし、木材が濡れるリスクもあるため、天気予報のチェックは欠かせません。
また、仏滅や三隣亡といった日は吉凶を表す暦注の中でも土木建築関係の凶日とされています。基本的にはそういった日を避けた上でお客様の希望日に合わせて日程を決定します。
- 土台・床敷き後の工程
上棟の前には、基礎工事が完了し、その上に「土台・床敷き」と呼ばれる工程が行われます。
土台とは、家の構造を支える最初の木材であり、これが正しく据えられていないと、その後の建物全体の精度に大きく影響します。リモート検査にて土台の敷き間違えや水平精度が保たれているか等をしっかりと確認し上棟に備えます。
土台・床敷き~上棟日までの間の期間内に敷いた土台や床合板が雨で濡れないように、水が染み込まないようにブルーシート等で養生を行います。
また、現場の敷地に余裕がある際は上棟日前に事前に壁のパネル等を敷地に置いて当日の作業の円滑化を図ります。

- 上棟当日のスケジュール(1日の流れについて)
1.1階の壁の組み立て作業
8:00~11:00

外周壁と内部の間仕切り壁を組み立てる作業をします。
クレーンを使用し、壁のパネルを吊るすことで重たい構造部材の組み立てを可能にしています。
通りを確認し、壁が傾いていないかををチェックすることで通り芯と壁とのズレを無くします。
また、壁の合板を施工する際の釘ピッチの間隔が適切かどうかを現場監督は目視・計測・撮影でチェックを行います。

2.2階の床・壁の組み立て作業
11:00~14:00

1階の壁が組み終わったら、同様に2階部分の床、壁、天井パネルを組み立てていきます。
TJIやLSLといった2階の床を構成する部材を組み立てていき、その上に2階の床合板と呼ばれる構造用の部材を敷いていきます。

「かけや」という通常より大きいサイズの木製のハンマーを用いて床合板を叩いて押し込み、床合板同士に隙間が生じないように組み立てていきます。これらも一つ一つ職人さんが手作業で行っています。
その後に釘打ち機を使い、壁部材と同様に所定のピッチで施工を行っていきます。

2階の床が組み終わったら次に、2階の壁を組み立てていきます。
2階の壁も1階の壁と同じ要領で組み立てていきます。

1階のときと同様に壁の合板を施工する際の釘ピッチの間隔が適切かどうか目視・計測・撮影によりチェックを行っていきます。
1階~2階にかけて組み立てた部材が金物により漏れなく緊結が行われているかを確認します。

3.屋根組み・躯体工事完了
14:00~17:00
2階の天井根太と言われる2×4部材で構成された2階の天井用の構造部材を組み立てていきます。

その後に妻壁や小屋束・小屋梁・屋根梁といった小屋組を構成する部材を組み立てていきます。

構造用の部材が金物で漏れなく緊結されているかをしっかりと目視・撮影にて確認していきます。

その後に垂木と呼ばれる屋根を構成する部材を組んでいきます。
垂木についても壁や床部材と同様にパネル化することで、現場での施工の円滑化を図っています。
垂木は、建物の一つ一つの屋根の形状(勾配、谷や棟の位置)によって異なり、施工が難しいため、細心の注意をはらって施工を行うようにします。

垂木の施工後も同様に金物による緊結が正しく行われているかを確認していきます。
「あおり止め金物」といった名称の緊結部材を使用し、垂木と2階の壁合板の緊結を行っていきます。

次に野地板と呼ばれる部材を先ほど施工した垂木に貼り付けていきます。
2階の床合板と同様に職人さんが釘打ち機を使い、ひとつひとつ手作業で打ち込んでいきます。

野地板を全部貼り終えたらいよいよ完成です。

上棟後に天候が崩れた場合等を考慮し、ブルーシートで屋根や壁の養生を行います。

これにて上棟の終了です。わずか1日という時間の中で行い、現場の状況が目まぐるしく変化するため、初めてご覧になられるお客様は現場の状況の変化をより一層楽しんでいただけると思います。
最後に近隣に木材の破片や釘等の飛散物が飛んでいっていないか、ゴミ等が放置されていないかを確認して終了となります。
- 上棟の際に使われる建築部材について紹介
次にちょっとした豆知識として上棟の際に使われる構造部材を一部紹介したいと思います。
まず、はじめにこちらはTJIという名称の部材です。


2階の床を構成する部材となっており、部材断面の形がアルファベットの「I」のような形をしています。この形は、縦方向(ウェブ:web)が広く、上下のフランジ(flange)が太い構造のため、曲げの応力に対して非常に強いといった特徴を持っています。
そのため床の上に人や物が乗ったときの部材にかかる応力(TJIを上下方向に曲げる力)に対抗できるため、合理的な構造と言えます。
建築物は自らの荷重や外力に対して抵抗できるかが強度をもたらす上での大きな鍵となっているためそういった構造は必要不可欠と言えますね。
次に紹介するのは、構造用の梁部材です。

集成梁と呼んでおり、ベイマツという樹種でできています。
ベイマツの特徴としましては、他の木材と比べてやや重みがあり、それと合わせて強度があるも比較的加工が行いやすいといった特徴をもっています。
集成材の部材の構成としては、5~50㎜程度のひき材を繊維方向を変えながら積層をした材料となっています。材料を積層することで大梁のような非常に長い材長や幅の広い断面寸法を要求される部材の生成をすることが可能となっています。
また、構造用以外にも化粧梁として吹き抜け等に設け、塗装を行うことで可愛らしさと迫力の両方を体感することもできます。

5.まとめ 「家が建つ」を体感する一日
上棟は、まさに「家が建つ日」として、お客様にとって一生の思い出に残る一日になります。
大工さんたちの熟練の技と、チームの連帯によって朝には何もなかった場所に夕方には家のかたちが現れる。その感動をぜひ味わっていただきたいと思います。
今回はこれで以上となります(笑)






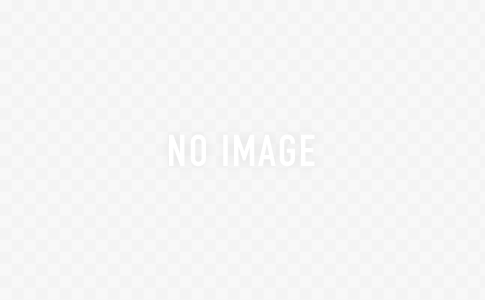







コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。