岩手のような寒冷地で冬に寒くない快適な暮らしを実現するために、大きな窓を採用したい場合、断熱性との両立が重要になります。
断熱性に優れたサッシ枠+断熱性に優れたガラス+サッシの断熱性を損なわない施工
を選び組み合わせることで、暖かさを保ちながら開放的な空間を作り出すことができます。ここでは、岩手のような寒冷地における高断熱で大きな窓選びについて、北欧の家の大きな窓事例や当社の施工例など交えてお伝えします。寒冷地でも大きな窓を取り入れた明るく暖かい住まいづくりのヒントにしてください。
人気のサッシ枠の見えない大きな窓
ほんの少し前に、関東圏で見学させていただいた家の窓を観てください。

FIXではありますが、ガラス1枚が大きく吹き抜けの壁面全体を窓ガラスにすることで圧巻の視界を室内に取り込んでいます。そして、何と言ってもサッシ枠が室内から見えないので、まるでガラスだけがはめ込みされているようにスッキリ見えます。
これはこれで凄い素敵な見せ方だなあ、と惚れ惚れしながら観てしまいます。でもここで岩手県にこれを建てる勇気は私にはないかなとも感じてしまいます。
というのも、寒冷地で不安に感じるリスクは2つ。
➀この大きなガラス面はペアガラスだからできるサイズであること。
➁サッシ枠が室内から見えないということは、基本サッシ枠は外付けであること。
寒冷地において、これらの弱点を克服できるアイデアは、今の私にはないからです。
北欧の家に設置された大きな窓
寒冷地と言えば、お手本したいのは北欧でようか。そこで北欧フィンランドの高断熱住宅の大きな窓の事例を観てみましょう。高断熱性能を持つ大きな窓を設置することには多くのメリットがあります。一般的に窓は熱の出入りが最も多い箇所ですが、北欧レベルの高断熱技術を採用した大きな窓なら、暖かさを保ちながら開放的な空間を実現できます。

北欧と同じような気候である寒冷地において高断熱の大きな窓を取り入れるメリットは、まず第一に写真にあるような豊かな採光が挙げられます。特に冬の日照時間が短い北欧では、南面の大きな窓から取り込む太陽光が室内を明るく照らし、自然の暖かさも得られるのです。また、トリプルガラスやクワトロガラスガラスを使用することで、窓からの熱損失を最小限に抑えながら日射熱を取り込むことができるのです。さらに、窓からの景色を存分に楽しめることで、室内にいながら四季の変化を感じることができ、厳しい寒さの中でも美しい雪景色も魅力的な眺めとなっているはずです。
採光と暖房効率の向上
南面に設ける高断熱の大きな窓の最大のメリットは、豊富な自然光を室内に取り込めることです。冬の日照時間が短くなりがちな北欧の人たちは、昔から断熱性能の高い大きな窓があれば限られた日照時間でも効率よく光を取り込むことを当たり前のように知っています。

これにより、照明の使用使用量を減らせるだけでなく、パッシブソーラーの効果で暖房効率も向上します。高断熱ガラスは太陽光のエネルギーを室内に取り込みながら、室内の熱が外に逃げるのを防ぐため、寒冷地での暖房費削減にも貢献します。また、明るい室内空間は精神的にも良い影響をもたらし、冬の閉塞感を軽減する効果も期待できますよね。
開放感と眺望の確保
北欧の人たちにとって、高断熱の大きな窓のもう一つの魅力は、室内に開放感をもたらし、外の景色を存分に楽しめることです。窓が小さいと冬の間は閉じこもった印象になりがちですが、大きな窓があれば室内にいながら広がりを感じられます。

特に、写真のような川の流れる景色や森林、山々などの自然豊かな北欧では、四季折々の美しい風景を窓枠いっぱいに取り込むことも欠かせないものようです。高断熱の大きな窓を設置することで、寒さを気にせず、一年を通じて自然とのつながりを感じながら生活することが可能にしています。また、室内が広く感じられる効果もあるため、実際の床面積以上の空間的余裕を感じさせる設計が可能になります。
では、北欧のような大きな窓を寒冷地である岩手で採用するにはどうするか?
寒冷地の高断熱窓に求められる窓の性能
寒冷地で大きな窓を設置する際には、樹脂トリプルガラス並みの高い断熱性能が必須条件となります。一般的な窓では断熱性能が低く、室内の暖かい空気が窓から逃げていくため、高断熱仕様の窓を考えなければなりません。
ここから当社の成功事例を紹介しなが話を進めます。

これは上部のアールデザインに重きを置いた南面に設けられた大きな窓です。
寒冷地での窓選びは、断熱性を示すU値(熱貫流率)が重要な指標となります。U値は数値が小さいほど断熱性能が高いことを示し、寒冷地で採用するサッシならトリプルガラス樹脂で0.8〜1.3 W/㎡K程度の低いU値を持つ窓が理想的です。また、結露防止性能も重要で、トリプルガラスであってもサッシ枠またはその周囲(ψinstall)から冷やされ、窓ガラスの一番の急所であるガラス端に室内の空気が触れると結露が発生し、カビやダニの温床になる可能性があるため注意が必要です。最近では目に見えない夏型の結露が危惧されるようにもなっています。
高断熱窓は窓全体の性能バランスを保ち、室内側の表面温度を高くし、結露の発生を抑制するのが基本です。さらに、気密性も重要な要素で、窓の隙間から冷気が侵入すると体感温度が下がり、暖房効率も悪化するため、建具とサッシ枠の高い気密性を持つガスケットの数や素材も窓選びに大切になります。
断熱性(U値)と日射熱取得率
寒冷地岩手で高断熱の大きな窓を選ぶ際、最も重視すべき性能は断熱性能です。窓の断熱性能は「U値」(熱貫流率)で表され、この数値が小さいほど熱を通しにくく、断熱性能が高いことを意味します。寒冷地では、U値が0.8〜1.3 W/㎡K以下の窓が推奨されています。さらに、日射熱取得率(η値)も重要な指標です。この値が高いほど太陽の熱エネルギーを室内に取り込むことができ、冬の暖房負荷を軽減できます。寒冷地では、断熱性を保ちながら日射熱も取り入れられるバランスの良い窓が理想的です。最新の高断熱窓は、アルゴンガス、Low-E複層ガラスやトリプルガラスを採用し、高い断熱性と適切な日射熱取得を両立させています。
寒冷地向け高断熱の大きな窓の種類
寒冷地で使用する大きな窓には、いくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解して、住まいのスタイルや予算に合った最適な窓を選びましょう。

写真の大きな窓はトリプルガラスの木製サッシです。このサッシのスペックは、
Low-Eガラス+16kr(クリプトンガス)+透明ガラス+16kr(クリプトンガス)
最たるものが日本にはないスーパースペーサーと言うかなり断熱性の高いガラススペーサーを採用。
また、木製サッシ窓は自然素材である木の低い熱伝導率を活かした窓で、断熱性だけでなくデザイン性も高いのが特徴です。さらに、内側に木肌が見えることで、見た目の美しさと断熱性を兼ね備えています。
一般的には、寒冷地に適した高断熱の大きな窓として、まずトリプルガラス窓が挙げられます。これは3枚のガラスの間に断熱効果のあるアルゴンガスを封入した構造で、最も高い断熱性能を誇ります。次にLow-E複層ガラス窓があり、特殊金属膜をコーティングしたガラスを使用することで、熱の出入りをコントロールします。アルミに比べて熱伝導率が低い樹脂製のサッシを使用することで熱橋を減らし断熱性を高めている、とここまでなのが現状です。
寒冷地の高断熱の1・2階通しデザインの大きな窓
寒冷地における高断熱の大きな窓の施工事例をもう一つ紹介します。リビングに面した南側に大きな窓を設置するケースです。これにより、太陽光をたっぷり取り込みながら、窓の高い断熱性能で暖かさを保つことができます。例えば、トリプルガラスと樹脂サッシ、さらに木製サッシのようなカラー樹脂サッシを組み合わせた1階から2階まで一体にデザインされたような窓デザインです。

「ような」というのは、そのように見えるようにしているだけで、1階はコンビネーションデザインの一体サッシ、2階も連窓デザインの一体サッシ、この二つのサッシを一体に見せているのです。
1階と2階の間にある横架材部分をサッシのカラー面材と同じもので覆っている(ドイツサッシのノウハウ)ので、色・質感ともにまったく同じものなので違和感がないはずです。
寒冷地で高断熱の大きな窓を活かす住まいづくり
寒冷地での高断熱・大きな窓の選び方と活用方法についてまとめます。断熱性と開放感の両立で、寒冷地でも快適な住空間を実現するためにポイントをまとめます。
➀トリプルガラス面積限度
ぺガラスのようにガラス一枚の面積限度はかなり小さい。一般のガラス厚で言うと、2.5㎡くらいが限度です。
➁トリプルガラス破損時のリスクも
台風などでガラスが破損した場合のリスクを想像してみてください。大きなガラスが飛散した時の怖さは計り知れません。対策としては、費用はかかりますが強化ガラスの採用がおすすめします。
③ガラス交換時の費用リスク
ガラス交換費用もバカになりません。大きなガラスサイズなら交換費用も高額になります。3枚ガラスのうちの一枚が割れたとしても、割れたガラス部分は3枚ガラス全交換になりますので、そのことも念頭に入れた上でガラスサイズなどを検討してみてください。
以上のように、寒冷地における高断熱大きな窓を活かした住まいづくりでは、窓の性能や配置、サイズのバランスが重要です。高断熱性能を持つトリプルガラスや樹脂サッシなどを選択し、サッシの取り付け方法まで検討した上で、南面を中心に大きな窓を配置することで、太陽光による自然暖房効果と開放感を同時に得ることができるはずです。
現在でも、高断熱と言われるトリプルガラスの樹脂窓はガラス部分がダントツに断熱性能は高く、樹脂枠はその半分の性能、熱橋はもっと性能は低下します。そこに近い将来、北欧やドイツには4層ガラス並みの断熱性を持つガラスがあるのですから、日本に登場するのはそう遠い話ではないのかもしれない。
もしそうだとすると、
同時にガラス厚サイズ変更もフレキシブルに対応できるサッシ枠が求められる時代になるのかもしれません。




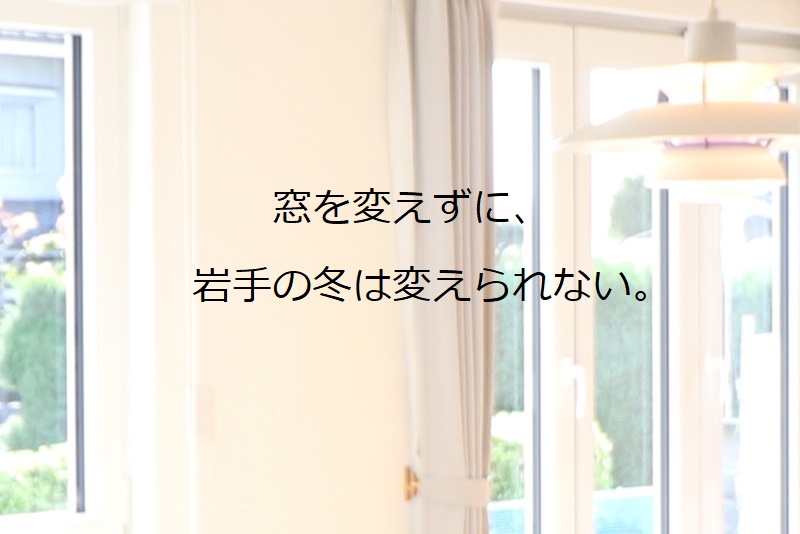








[…] 寒冷地における窓選びの重要性については、以下の記事も参考にしてみてください。 寒冷地だからこその高断熱の大きな窓の選び方 […]