昨夜も寒かった。。。
というわけで、計測中の最低気温をチェック。
岩手県 奥中山 -18.3℃
岩手県 玉山生出 -13.5℃
岩手県 盛岡市向中野 -10.2℃
岩手県 盛岡市永井 -5.5℃
岩手県 盛岡市松園 -11.6℃
岩手県 花巻市 -8.3℃
岩手県 石鳥谷 不検出!!?
以上、私の手元で確認した主な最低気温でした(笑
さて、
結露試験も本調子に向かい始めてきました。
しょっちゅう行ってられないので、
朝のデータ回収は4号の出勤時にお願いしている。
その際、回収時の状況写真もお願いしているのだが、、、
なんと3号自身の姿ばかりが窓ガラスに映っていて、
肝心の結露状況はよくわからん!
周囲が明るいとLow-Eガラスの反射がきつくて、
確かに撮りづらい。
ガラスに映し出されるいろんな必死の姿。
それ観てたらうれしくて笑えこそすれ、文句など言えませんでした^^
そんな彼女の回収してくれたものの顕著な部分のみを紹介すると・・・

ここの4枚のあとは、結露面積は縮小し結露の水滴は大きくなり垂れる状態に。
それは4枚目以降に外気温が上昇し始めたからかと。
この間の平均外気温は、-12℃以下。
だけど、この結露状況写真を観て、ふと疑問が・・
なんでだべ?
というのは、1月28日の結露状況だ。

この時点の外気温は、-5.9℃。
室内温度はほぼ同じ。
湿度はむしろ昨夜の方が高い。
この逆の減少はなぜに起こるわけ・・?
窓の本音が聞きたくなる。

そして昨夜の当社最高を誇る断熱窓。
この時点で、もう一つの樹脂のトリプルガラスは結露していた。
さて、同じトリプルガラスなのに、結露の有無が明快に分かれた。
ということは、わかっていたこととは言え、
ペアガラスであれトリプルガラスであれ、
ガラスの枚数はそれほど意味がないことになる。
頭ではわかっていても、実態に出会うことの意義は大きい。
少なくとも肉体思考派の私には(笑
結露に関して言えば、窓の性能=耐結露性能ではない。
今、国内サッシメーカーが性能を競い始めたばかり。
だけど、この耐結露の問題はどうもなおざりのような気がしている。
冬季の過乾燥を解決した先に、頭をもたげるのは窓の結露。
潤いのある、良好な室内環境に耐えうる窓スペックと施工法、
その理想のカタチはどこらへんに転がってるんだべか・・・
ときどき、窓の本音が聞きたくなる。





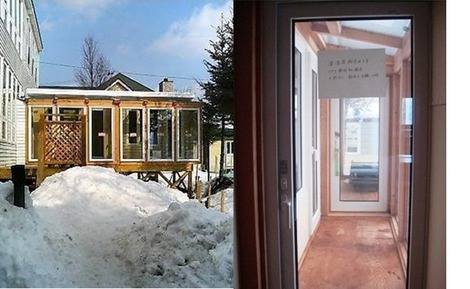






コメントを残す