断熱等級6,だとか7だとか、耐震等級など、視点を変えて深堀りし始めると、線状の熱損失、線状の強度不足、線状に存在するリスクは計算されないという矛盾に行き着くことがあります。計算上存在しないものとして扱われるからと言って無いことにはならない。
実性能が良ければそれでいいじゃない。計算を下回るわけではないのだから。
と自分に言い聞かせてきたけど、それもまた自分の中の矛盾だよなと気づく時がくるものです。
4年ほど前、当社で扱っているドイツサッシの性能試験を行ったことがあります。
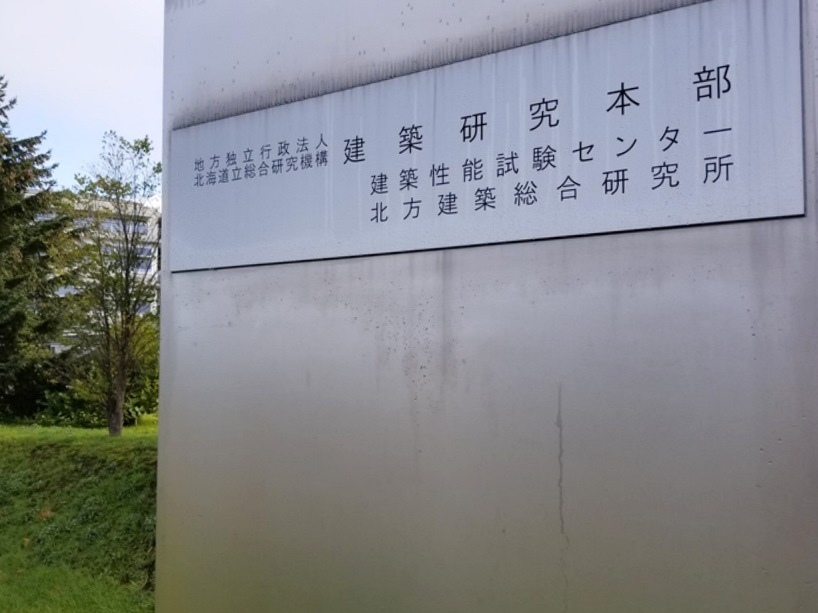
場所は北総研。

試験の事前相談から始めて試験方法、試験体の製作まで自社で行いチェレンジしたものの、ずっと感じてたことは、
田舎の一工務店がやることではないよなってこと。でした(笑
でも、それぞれの試験方法を見学していると、試験前に試験体をどのようにセットすべきか、そして試験でチェックされるポイントはどこなのか、など知ることができたのは、試験結果以上の学びになったのは自分的には大きな成果かなと思っています。
そして、あれから4年。
新たな試験?に挑戦しようとしています。それはJISなどにより決められた試験方法にはない評価方法を模索しなければなりません。
そのルートとして候補にあがったのが、特別評価方法認定というものです。
但し、それができるかどうかはまだわからない。
以下に、そのしくみの要約をコピペします。
特別評価方法認定の制度的枠組み
この認定の審査のためには、事前に分析や試験、測定などによる審査を行う必要があり、法令上これを単に「試験」といっております。この「試験」については、国土交通大臣の指定を受けた専門的機関(登録試験機関)が行い、その「試験」の結果について、証明書を交付することとなります。その後、特別評価方法認定を取得しようとする者は、その機関が交付した証明書を添えて国土交通大臣に特別評価方法認定の申請を行うこととなります。
そこで新たな試験機関選びから始めることに。
これまでの特別評価方法認定一覧リストを見ると、これまた
地方の工務店がやることじゃないのでは?だいそれてないか?と思えてきます(笑
正直、評価方法認定を受けられるかどうかはわからない。でもやるなら認定は受けられずとも最低限、「試験結果で性能を証明する」までは目指したいですよね。

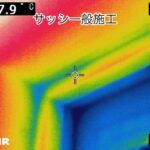



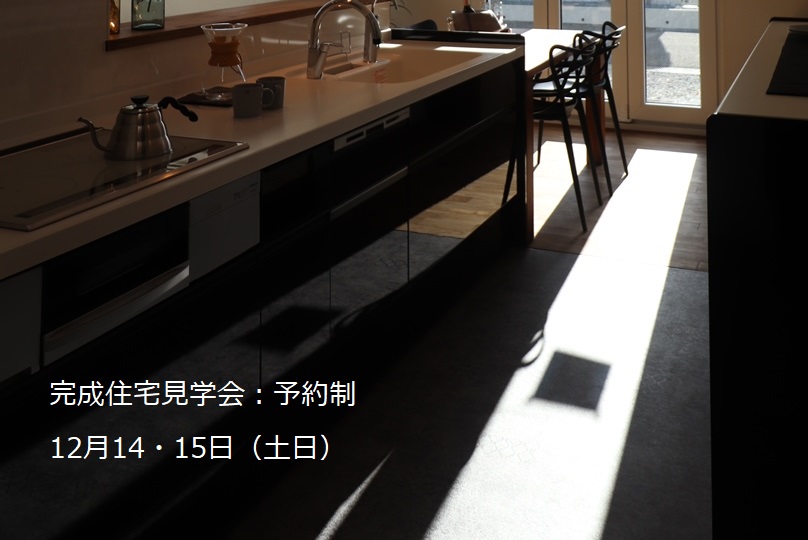







コメントを残す