フェノールフォーム「ネオマゼウス」二層張りでつくる、大共ホーム最高断熱レベルの現場から
当社は充填断熱や木構造部の熱橋リスク解消のため外張り断熱の有効性は試験施工などから認識していました。ところが当時の外張り断熱に使われる断熱材は当社が求める断熱性能では外張りが厚くなるというリスクに不安があり躊躇していたものです。
そんな状況のところに、旭化成建材からネオマフォームが登場します。
このネオマの断熱性能ならそれほど厚くしなくても性能は出せる!
ということから、ネオマフォームによる外張り断熱をメインとする高断熱住宅がスタートしました。
高断熱住宅は外張り断熱がメイン
断熱の重要性が見直され断熱等級6や7の住宅が登場した最近では外張り断熱層のことを”付加断熱”と呼ぶようになっています。これは充填断熱がメインであり、充填断熱にプラスする発想からきたものと思いますが当社は違います。
ひと頃、W断熱というワードだけが一人歩き、工事現場を見ると1㎝か2㎝程度の断熱材を外張りしているのをよく見かけたものです。これは無いよりは益しではあるものの、外に断熱を張る作業手間を考えると、作業に対する断熱性能のコスパは低いのに。。と感じたものです。
進化する外張り断熱施工
ドイツや北欧の断熱層を見たことがあるでしょうか?私はずっと観てきて最初に感じたのは
気候的には岩手や札幌とさほど違わないのに、なぜあれだけ厚い断熱層を持たせるのか。
最近では、ドイツ北欧は3層の断熱層は基本なのでは?と思うようになっています。その中でも外張り断熱(ウレタンボード)層10㎝、私が観た中での最大は20㎝施工まであったのです。そこで疑問が生じます。
この外張り断熱は、どのように施工すればこれだけの厚さを確保できるのか?
これを解決するヒントをドイツで見付けたのです。ヒントを得て、試験を開始しました。それら試験結果のデータから現在の外張り断熱の施工方法の原型が生まれることになります。
1. 岩手の冬を“セラミックヒーター1台で快適”にする挑戦
岩手の冬は、氷点下10℃を下回る厳しい寒さが続く地域。そんな環境の中でも、少ない暖房エネルギーで家全体を快適に保つために、大共ホームが挑戦しているのが「Ua値0.15」スペックの超高断熱住宅です。
この数値は、国の定める断熱等級7(Ua値0.20以下)を大きく上回る性能であり、岩手県内でもトップクラス。今回は、その最高断熱仕様の施工現場から報告しようと思います。現場では、その外側にフェノールフォーム断熱材「ネオマゼウス」を二層で張り重ねる“外張りダブル断熱構法”を採用しています。一日フレーミング(上棟)後に屋根工事と同じように、断熱材を雨に濡らすことの無いようできるだけ早い段階で外張り施工を心がけているので、壁の内部に高性能グラスウールを充填するのは外張り断熱施工より後になることが多いのではないかと思います。

できるだけ雨に濡れない状態で一日フレーミングから外張り断熱工事へと進行するのが基本。これが気温・湿度の影響を最小限に抑える大共ホーム独自の工程管理です。
2. 外張りダブル断熱の構造:内外の断熱層で家を包み込む
高断熱住宅の性能は、断熱材の「厚み」だけでなく、「連続性」と「気密性」で決まります。今回の施工では、室内側に高性能グラスウール16K(厚さ89mm)を充填し、外側にはフェノールフォーム(ネオマゼウス)60mm+45mmの二層張りを採用。合計で約195mmの厚みをもつ断熱壁が形成されます。
外張りフェノールフォームはλ=0.018W/mKという極めて低い熱伝導率を誇り、外壁の熱橋(ヒートブリッジ)をほぼゼロに近づけます。これにより、冬の冷気侵入だけでなく、夏の熱気の侵入も抑制。冷暖房効率を飛躍的に高めます。

現場に整然と積まれたネオマゼウス。1枚1枚が軽量で高剛性、施工時の寸法精度も高く、二層張りでもズレが生じにくい構造です。
3. 職人の精度が性能を決める:隙間ゼロの断熱施工
いくら高性能な断熱材を使っても、施工の精度が伴わなければ本来の性能は発揮できません。大共ホームでは、断熱施工の段階から職人が1枚ずつ密着度を確認しながら張り合わせ、さらにジョイント部を専用気密テープで処理しています。
とくに重要なのが、コーナー部やサッシまわりの納まり。断熱層が途切れると、そこから結露や熱損失が発生するため、断熱材の連続性確保が行われています。これにより、壁体全体が“ひとつの断熱カプセル”のように家を包み込みます。
外張り断熱を二層張りにする理由
気密テープで丁寧に処理された接合部。1本のラインが“家全体の断熱バリア”として連続し、熱橋を徹底的に排除します。
ここで注目して欲しいのが、なぜ外張りが二層なのかということ。

外張り断熱層は100mm厚を一層で張ることもできます。外張り断熱厚100mmなら、一層張りにしているハウスメーカーさんが一般的ではないでしょうか。外張り断熱施工を2回張るより1回で行う方が施工手間は安くなるわけですから自然な選択なのかもしれません。
ですがここで私たちは、経験値から敢えて手間はかかりますが二層張りを選択しました。その理由は、以下の2点です。
➀二層張りにすることで各層毎のジョイントをずらして張ることができます。
これにより経年収縮リスクを低減することができます。断熱性能はできるだけ長い期間保って欲しいですから。
➁二層張りにすることで窓周囲熱橋対策も容易になります。
殆どのハウスメーカーは気にしませんが、ドイツでは当たり前に対策されていることです。
外張り断熱層コーナー部を外面合わせとする納まり
当社では構造部を北米から習い、強度的にも合理的な外面合わせという施工法を採っています。その経験の延長上に外張り断熱層のコーナー部も成り立っています。

一般的には外張り断熱層コーナー部は別にカットしたものを張っているのをよく見かけます。それだとコーナー部のジョイントが2本多くなってしまいますのでそれを避けるため、写真のように外面まで外張り断熱材が届くようにしてカットしているわけです。
このように断熱層が分断されないので、サーモカメラで見ても温度ムラがほとんどありません。
4. 実測でわかる、岩手仕様の高断熱性能
この現場の仕様で試算された国交省のモデルプランにおける外皮平均熱貫流率(Ua値)は0.15W/㎡K。これは、国の基準で最も厳しい地域区分1〜2地域(北海道・東北北部)においてもトップクラスの性能です。
たとえば、一般的な高断熱住宅(Ua値0.46〜0.34)と比較すると、外気温−5℃の日における室内壁面温度差は約5〜7℃も小さくなります。体感的には、「暖房していることを忘れる」ほどの快適さです。
さらに、冷暖房エネルギー消費量のシミュレーションでは、従来仕様に比べて年間光熱費を約40〜50%削減できる見込み。岩手のような寒冷地では、この差がそのまま快適性とランニングコストの違いになります。
| 比較項目 | 一般的な断熱住宅 | 大共ホーム 最高断熱仕様 |
|---|---|---|
| 外壁構成 | 充填断熱のみ | 充填+外張りダブル断熱 |
| 使用断熱材 | 高性能グラスウール | グラスウール+ネオマゼウス |
| 断熱厚み | 約100mm | 約190mm(外張り含む) |
| UA値 | 約0.46〜0.34 | 0.15W/㎡K |
| 室内温度差 | 約6℃ | 1〜2℃以内 |
| 冬期光熱費 | 比較的高い | 約半分以下 |
5. 熱橋ゼロを目指す“細部までの断熱思想”
大共ホームでは、壁面だけでなく、窓まわりの熱橋対策(ψinstall)にも独自の特許施工を採用。ドイツ製トリプルガラスサッシとの組み合わせにより、窓まわりの冷気侵入を防ぎ、全体の断熱性能をさらに底上げしています。
外張り断熱層でサッシ枠(一部)まで覆う
外張り2層断熱の1層目の断熱工事を終了。窓周囲熱橋対策は外張り断熱層をサッシ枠まで覆うこの1層目が要となっている。#窓周囲熱橋#外張り2層断熱#ヒートブリッジ pic.twitter.com/QzFm65BIRz
— oyakata (@ooyakata11) August 1, 2024
外張り断熱層から連続で窓台まで覆う
窓周囲ヒートブリッジ対策のための、窓への工場での事前施工から現場での外張り断熱施工までの当社スタッフの連携作業を。
当社が行っている内付窓施工手順。窓下熱橋となる外張り断熱層補助桟を無くしてることと窓下木部枠を外張り断熱層から連続で包み込む施工法です。
この一連の作業を社員スタッフが連携することで端材利用&省力化しています。昨日一昨日投稿の断面と比較して観るとわかりやすいかもしれません。 pic.twitter.com/O6v5EkVNC7— oyakata (@ooyakata11) November 23, 2024
これにより、一般的に熱損失が大きい「窓周囲・基礎・屋根の取り合い部分」でも安定した温熱環境を維持。暖房の立ち上がりも早く、エアコン1台、もしくはセラミックヒーター1台でも家全体が均一に暖まります。
現場では、工事途中と完成時に気密測定を実施。内外温度差のある冬季や夏季にはサーモカメラ検査を実施し、内部結露のリスクをゼロに。これら実測で裏付けされた性能が、岩手という寒冷地での安心感につながるのではないかと考えています。
6. 施工から見える“未来基準の家づくり”
このUa値0.15の仕様は、単なる性能競争ではなく、将来のエネルギー価格上昇やカーボンニュートラル社会への備えでもあります。断熱性能が高ければ、再生可能エネルギー(太陽光+ヒートポンプ)との組み合わせで、年間の暖房費を限りなくゼロに近づけることも可能になります。
さらに、断熱等級7を超える家は、国の補助金制度や認定住宅(LCCM住宅、ZEH Oriented など)の対象にもなりやすく、将来の資産価値も高く維持できます。
大共ホームでは、こうした先進的な断熱仕様をー“岩手の標準”にすることーを目標に、研究開発と現場検証を継続しています。
7. まとめ:岩手の寒さを味方にする家
岩手の冬は厳しい。しかし、その寒さをドイツや北欧の先進技術を知り輸入と技術導入し続けたきた工務店だからこそ、本当の快適さを追求できる。今回のUa値0.15仕様の家は、
-
断熱等級7を超える性能、
-
ダブル外断熱+充填断熱による極めて高い温度安定性、
-
職人の手による精密な施工連携、
これらすべてが組み合わさって生まれる“岩手の極暖住宅”です。
「暖房していることを忘れる家」——それが、大共ホームが目指す“冬のあたりまえを変える住まい”です。










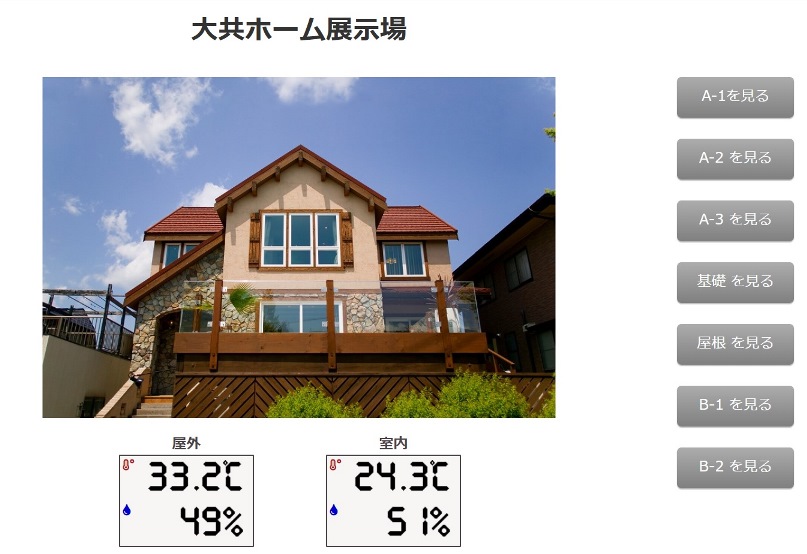




コメントを残す